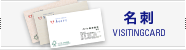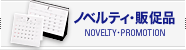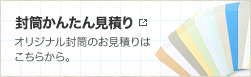※成木になるまで8〜10年という、成長の早いユーカリやアカシアなどの「広葉樹」を使用しているので、比較的早いサイクルで土地を有効利用することができます。

アオイ科ハイビスカス属の一年草で別名をホワイトハイビスカスとも呼ばれます。成長が極めて早く、約半年で茎の太さ約3〜5cm、高さ3〜4mに達します。皮の部分(靱皮)、芯の部分、全て紙の原料として利用できるなどまさに木材に替わる最適な非木材資源とされています。ケナフは西アフリカ原産と言われており、古くはエジプトのミイラの包帯にも使われていた植物です。ケナフは数千年も前から利用され、繊維を被服材料として使われたり種から油(約20%)を採取したりしていた様です。
非木材繊維生成植物中で最も成長が速く、単位面積当たりの繊維収穫量が多く、かつ木材パルプに最も近い性能や風合いが得られるので資源植物として大きな期待をもたれています。成育中も二酸化炭素の吸着量が木の数倍あり、地球温暖化の主要原因と言われる二酸化炭素の増加を抑えることにも役立ちます。また土中の窒素やリンの吸収効率も大きく、環境浄化能力の優れた性質を持ちます。
琵琶湖の浅瀬にはえる草「ヨシ」が原料の紙です。枯れたヨシを加工して、ヨシ紙「レイクパピルス」が誕生します。
湖の浅い部分に生えるヨシは、春に新芽を出して冬に枯れるまでの間、湖の水を絶えず吸い上げて窒素やリンなどを栄養分として吸収するので、水がきれいになります。しかし、ヨシは春に芽吹き、冬には枯れてしまいます。この枯れたヨシをそのままにしておくと、ヨシは腐食し、ヘドロとなりメタンガスを発生する原因ともなります。
ヨシを刈り取る事によって、翌年の春の新芽を出しやすくし、琵琶湖の水質悪化を抑え、湖水を浄化します。レイクパピルスの原料はこの刈り取られたヨシです。
搾汁後のサトウキビを使用。サトウキビは、CO2の吸着固定に優れ、地球温暖化防止に役立つ、イネ科の多年生植物です。
下記製品は植林木・非木材紙を使用した製品です。詳しくは各製品ページをご覧ください。